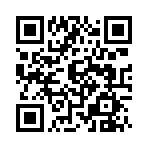寒い!それは誰でも同じか!どうやって道を開くか!
あなたは時代とどのように立ち向かいますか?
物凄い寒さ。東京でこのような寒さは滅多にない。ということは、雪国はもっと生活困難な状況に置かれているはずだ。情報が一切入ってこない。除雪だけでも緊急措置を取らなくてはいけないと思うのだが政府は動かない。政治は誰のためにあるのかみんな真剣に考えよう。雪下ろし行動隊を設置し、弱者を救済しようという熱意と行動力がほしい。今の政治家に求めては無理か?どうすれば?

風が強く寒い日の富士山は表情が変わるからと思いカメラを持って自転車で大好きな場所に出かける。それは沢の台歩道橋・三鷹7中横の104段階の上だ。とにかく寒い。変化を取ろうと待った!マッタが限界!それが今日の写真。冷たい表情の富士山、晴れ晴れとした富士山、我々が自然とどう向かい合っていくかが問われる時代である。3・4人の若者が自転車で走ってきて「霊峰富士だ!」と声を上げていたのが印象的だった。
マツンの同感 読売新聞投稿 気流から
役立つ学校だより 人生訓に感じ入る
僧侶 小林隆猛 53 (東京都葛飾区)
 児童委員をしている関係で、地域の小中学校から毎月、「学校だより」が届けられる。わら半紙1枚程度数ものだが、学校の話題を中心に、季節の話などが掲載されている。中でも、校長や副校長が書いた文章には、教えられることが多い。
児童委員をしている関係で、地域の小中学校から毎月、「学校だより」が届けられる。わら半紙1枚程度数ものだが、学校の話題を中心に、季節の話などが掲載されている。中でも、校長や副校長が書いた文章には、教えられることが多い。
雨の日に互いの傘を外側に傾けヽ濡れないように擦れ違うことを「傘かしげ」といい、他人を思いやる知恵から生まれた言葉だと知ったのも、学校だよりだった。
年初には、「あいさつは魔法の言葉」という文章にはっとさせられた。人生訓や人柄がにじみ出る内容には、さすがだと感じ入るばかりだ。
学校だよりは、保護者だけでなく、町内会の回覧板や掲示板を通しても読むことができる。多くの人の目に触れて、地域にある学校を身近に感じ取ってもらいたい。
私が思うのは、校長・副校長だけでなく、教職員全体が情報を発信すべきである。それができない現実を誰かが書かなくてはいけない。でも、それだけリスクがあり勇気がある教員は何人いるか。事務の立場、図書館の司書の立場、給食の関係者など知りたい情報はいっぱいある。情報化社会の中、使い勝手と主人公のやる気だ。子供が主人公の社会に戻るべきだ。出世に窮している輩では日本を救えない。
マツンの夢 こんな社会が懐かしい 夢がある もどってみたい
鈴木ヒロミツ気楽にいこう 1971年(昭和46年~のCM)
気楽にいこうよ おれたちは、
あせってみたっておなじこと~~
のんびり行こうよおれたちは
なんとかなるさ 世の中は・・・
くるまはガソリンで動くのです Mobil石油』
私は年代が同じだったので肝臓がんで亡くなったのはショックだった。彼の書いた本が出版された。日専校に出張の上野駅で買った。常磐線が混んでいて満席。私の横は子連れ。水戸まで一緒だったのだが、別れ際お子さんに「おじさんなぜ泣いているの?」と聞かれた。鈴木ヒロミツの本を読んでいて感動して周りを気にしていない証拠だった。確実に時代は変化している。車社会こそ壮絶な変化。ハイブリッド・電気自動車が産業構造を大きく変えてしまう。変化をしっかり見て気楽にいこう。
 午前中はイカリクリニックで検診。成城らしからぬ、いや、昔の成城学園の自然・「道」と出会った。成城の香りがここにはある。大岡昇平の「成城だより」に書かれているところだ。また夕方カメラで夕陽を撮ろうとした
午前中はイカリクリニックで検診。成城らしからぬ、いや、昔の成城学園の自然・「道」と出会った。成城の香りがここにはある。大岡昇平の「成城だより」に書かれているところだ。また夕方カメラで夕陽を撮ろうとした href="http://www.nao.ac.jp/" target="_blank">国立天文台の「道」は一番好きな癒される場所。
href="http://www.nao.ac.jp/" target="_blank">国立天文台の「道」は一番好きな癒される場所。
道といえば武者小路実篤さんの 『この道より我を生かす道はなし、この道を行く』が頭に浮かぶ。
自分を生かせると思える道を 信じて進んでいけたら、幸せでしょう。
物凄い寒さ。東京でこのような寒さは滅多にない。ということは、雪国はもっと生活困難な状況に置かれているはずだ。情報が一切入ってこない。除雪だけでも緊急措置を取らなくてはいけないと思うのだが政府は動かない。政治は誰のためにあるのかみんな真剣に考えよう。雪下ろし行動隊を設置し、弱者を救済しようという熱意と行動力がほしい。今の政治家に求めては無理か?どうすれば?

風が強く寒い日の富士山は表情が変わるからと思いカメラを持って自転車で大好きな場所に出かける。それは沢の台歩道橋・三鷹7中横の104段階の上だ。とにかく寒い。変化を取ろうと待った!マッタが限界!それが今日の写真。冷たい表情の富士山、晴れ晴れとした富士山、我々が自然とどう向かい合っていくかが問われる時代である。3・4人の若者が自転車で走ってきて「霊峰富士だ!」と声を上げていたのが印象的だった。
マツンの同感 読売新聞投稿 気流から
役立つ学校だより 人生訓に感じ入る
僧侶 小林隆猛 53 (東京都葛飾区)
 児童委員をしている関係で、地域の小中学校から毎月、「学校だより」が届けられる。わら半紙1枚程度数ものだが、学校の話題を中心に、季節の話などが掲載されている。中でも、校長や副校長が書いた文章には、教えられることが多い。
児童委員をしている関係で、地域の小中学校から毎月、「学校だより」が届けられる。わら半紙1枚程度数ものだが、学校の話題を中心に、季節の話などが掲載されている。中でも、校長や副校長が書いた文章には、教えられることが多い。雨の日に互いの傘を外側に傾けヽ濡れないように擦れ違うことを「傘かしげ」といい、他人を思いやる知恵から生まれた言葉だと知ったのも、学校だよりだった。
年初には、「あいさつは魔法の言葉」という文章にはっとさせられた。人生訓や人柄がにじみ出る内容には、さすがだと感じ入るばかりだ。
学校だよりは、保護者だけでなく、町内会の回覧板や掲示板を通しても読むことができる。多くの人の目に触れて、地域にある学校を身近に感じ取ってもらいたい。
私が思うのは、校長・副校長だけでなく、教職員全体が情報を発信すべきである。それができない現実を誰かが書かなくてはいけない。でも、それだけリスクがあり勇気がある教員は何人いるか。事務の立場、図書館の司書の立場、給食の関係者など知りたい情報はいっぱいある。情報化社会の中、使い勝手と主人公のやる気だ。子供が主人公の社会に戻るべきだ。出世に窮している輩では日本を救えない。
マツンの夢 こんな社会が懐かしい 夢がある もどってみたい
鈴木ヒロミツ気楽にいこう 1971年(昭和46年~のCM)
気楽にいこうよ おれたちは、
あせってみたっておなじこと~~
のんびり行こうよおれたちは
なんとかなるさ 世の中は・・・
くるまはガソリンで動くのです Mobil石油』
私は年代が同じだったので肝臓がんで亡くなったのはショックだった。彼の書いた本が出版された。日専校に出張の上野駅で買った。常磐線が混んでいて満席。私の横は子連れ。水戸まで一緒だったのだが、別れ際お子さんに「おじさんなぜ泣いているの?」と聞かれた。鈴木ヒロミツの本を読んでいて感動して周りを気にしていない証拠だった。確実に時代は変化している。車社会こそ壮絶な変化。ハイブリッド・電気自動車が産業構造を大きく変えてしまう。変化をしっかり見て気楽にいこう。
 午前中はイカリクリニックで検診。成城らしからぬ、いや、昔の成城学園の自然・「道」と出会った。成城の香りがここにはある。大岡昇平の「成城だより」に書かれているところだ。また夕方カメラで夕陽を撮ろうとした
午前中はイカリクリニックで検診。成城らしからぬ、いや、昔の成城学園の自然・「道」と出会った。成城の香りがここにはある。大岡昇平の「成城だより」に書かれているところだ。また夕方カメラで夕陽を撮ろうとした href="http://www.nao.ac.jp/" target="_blank">国立天文台の「道」は一番好きな癒される場所。
href="http://www.nao.ac.jp/" target="_blank">国立天文台の「道」は一番好きな癒される場所。道といえば武者小路実篤さんの 『この道より我を生かす道はなし、この道を行く』が頭に浮かぶ。
自分を生かせると思える道を 信じて進んでいけたら、幸せでしょう。