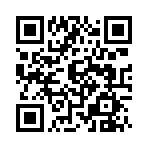台風26号が関東を直撃か
台風26号 10年に1度の勢力を保ち、非常に激しい雨風を伴う

気象庁によると、台風は中心気圧が低いほど強い風が吹く。
950ヘクトパスカルで伊豆半島へ上陸、関東を通過した平成16年10月の台風22号では猛烈な風雨となり、死者7人、行方不明者2人、負傷者170人と大きな被害が出た。
日記を調べてみた。平成16年(2004年)10月9日(土)、10日(日)、11日(月・祭)の三連休の初日だった。
それでも大きな被害を受けた。
今回は平日の一番混む時間帯。三鷹の小・中学校は休校とした。
暴風雨が予想されるので無駄な動きは止めた方がいいだろう。大都会の台風直撃は想定外が起こりそう。
長次郎日記では、「台風で≪多摩川大氾濫≫するかもよ?」と書かれている。
大切な課題が置き去りになっていないか SNS

10月8日、東京・三鷹で女子高生(18)の刺殺事件
6日前に私がこの事件で考えたことはつぎのようなことだった。
安全・安心な街三鷹に油断か。
家庭・学校・警察が連絡をとりながらも事件を防げなかった。
おのおのの部署に責任回避の姿勢がなかっただろうか。
国民の不安を拭いさる努力を早急にしないと。
相談があったらきちんと事情聴取し、情報を収集・整理し、関係部署に対応できる体制を確立する。
窓口の一本化。責任の一本化。
マスコミの責任は。扇動のみ。何をなすべきか、徹底的に特集を組む。
事件の原因をフェイスブックに押し付けている。
SNSの危険性ばかり強調。
正しい使い方、リテラシー教育の徹底。
「友だち」申請・承認は慎重に。
基本は自分を守る意識。
知って欲しい、便利なツールということを。
子どものいいなりで安易にスマホiPhoenを買い与えていないか。
子ども世界ではスマホiPhoenを持っていないと仲間に入れない。
子どもの基本はゲーム。
子どもの世界ではライン、スカイプ、フェイスブック、ツイッターは当たり前。
しかし16日現在、深刻で大変なことになっている。
犯罪被害者の実名報道と、さらに被害者のプライバシーがネットで拡散される「二次被害」。
基本的な考え方を永野和夫先生が述べている。
ネットワーク社会になり、何かの活動のために、場所や時間を共有しなければならないという条件が外れ、時間と空間を超えてコミュニケーションができるようになり世界は広がったといわれる。確かにその通りだが、それはFace to Faceのコミュニケーションができることを前提とした拡大であるべきだろう。その意味では教育活動では、原点に返った人と人とのふれあいを中心とした活動に力を入れておかなければならないとつくづく思う。人を生身の心をもつ人間として感じていれば、たとえその道具を使いこなしていても、人の命に危険が迫っていることもわからないほど感覚がマヒすることはないだろう。
スマートフォンといえば、最先端の携帯情報端末、ソフトの開発も含め、もっと知的で創造的な道具として使えるよう、発展してほしいものである。

私たち大人ももっとSNSの実態を知る必要があるだろう。
子どもたちだけに責任をなすりつけるのはいかがなももか。
情報リテラシー教育が追い付かない。ネットリテラシー教育か。
大人が知らない、子供をめぐるSNSの実態とは-。

気象庁によると、台風は中心気圧が低いほど強い風が吹く。
950ヘクトパスカルで伊豆半島へ上陸、関東を通過した平成16年10月の台風22号では猛烈な風雨となり、死者7人、行方不明者2人、負傷者170人と大きな被害が出た。
日記を調べてみた。平成16年(2004年)10月9日(土)、10日(日)、11日(月・祭)の三連休の初日だった。
それでも大きな被害を受けた。
今回は平日の一番混む時間帯。三鷹の小・中学校は休校とした。
暴風雨が予想されるので無駄な動きは止めた方がいいだろう。大都会の台風直撃は想定外が起こりそう。
長次郎日記では、「台風で≪多摩川大氾濫≫するかもよ?」と書かれている。
大切な課題が置き去りになっていないか SNS

10月8日、東京・三鷹で女子高生(18)の刺殺事件
6日前に私がこの事件で考えたことはつぎのようなことだった。
安全・安心な街三鷹に油断か。
家庭・学校・警察が連絡をとりながらも事件を防げなかった。
おのおのの部署に責任回避の姿勢がなかっただろうか。
国民の不安を拭いさる努力を早急にしないと。
相談があったらきちんと事情聴取し、情報を収集・整理し、関係部署に対応できる体制を確立する。
窓口の一本化。責任の一本化。
マスコミの責任は。扇動のみ。何をなすべきか、徹底的に特集を組む。
事件の原因をフェイスブックに押し付けている。
SNSの危険性ばかり強調。
正しい使い方、リテラシー教育の徹底。
「友だち」申請・承認は慎重に。
基本は自分を守る意識。
知って欲しい、便利なツールということを。
子どものいいなりで安易にスマホiPhoenを買い与えていないか。
子ども世界ではスマホiPhoenを持っていないと仲間に入れない。
子どもの基本はゲーム。
子どもの世界ではライン、スカイプ、フェイスブック、ツイッターは当たり前。
しかし16日現在、深刻で大変なことになっている。
犯罪被害者の実名報道と、さらに被害者のプライバシーがネットで拡散される「二次被害」。
基本的な考え方を永野和夫先生が述べている。
ネットワーク社会になり、何かの活動のために、場所や時間を共有しなければならないという条件が外れ、時間と空間を超えてコミュニケーションができるようになり世界は広がったといわれる。確かにその通りだが、それはFace to Faceのコミュニケーションができることを前提とした拡大であるべきだろう。その意味では教育活動では、原点に返った人と人とのふれあいを中心とした活動に力を入れておかなければならないとつくづく思う。人を生身の心をもつ人間として感じていれば、たとえその道具を使いこなしていても、人の命に危険が迫っていることもわからないほど感覚がマヒすることはないだろう。
スマートフォンといえば、最先端の携帯情報端末、ソフトの開発も含め、もっと知的で創造的な道具として使えるよう、発展してほしいものである。

私たち大人ももっとSNSの実態を知る必要があるだろう。
子どもたちだけに責任をなすりつけるのはいかがなももか。
情報リテラシー教育が追い付かない。ネットリテラシー教育か。
大人が知らない、子供をめぐるSNSの実態とは-。